Survey or Interview植村 天受
泌尿器がんワクチン開発研究、
風通しのよい体制づくりに専心
Dedicated to developing vaccines for urological cancer— while fostering an open and transparent research environment.
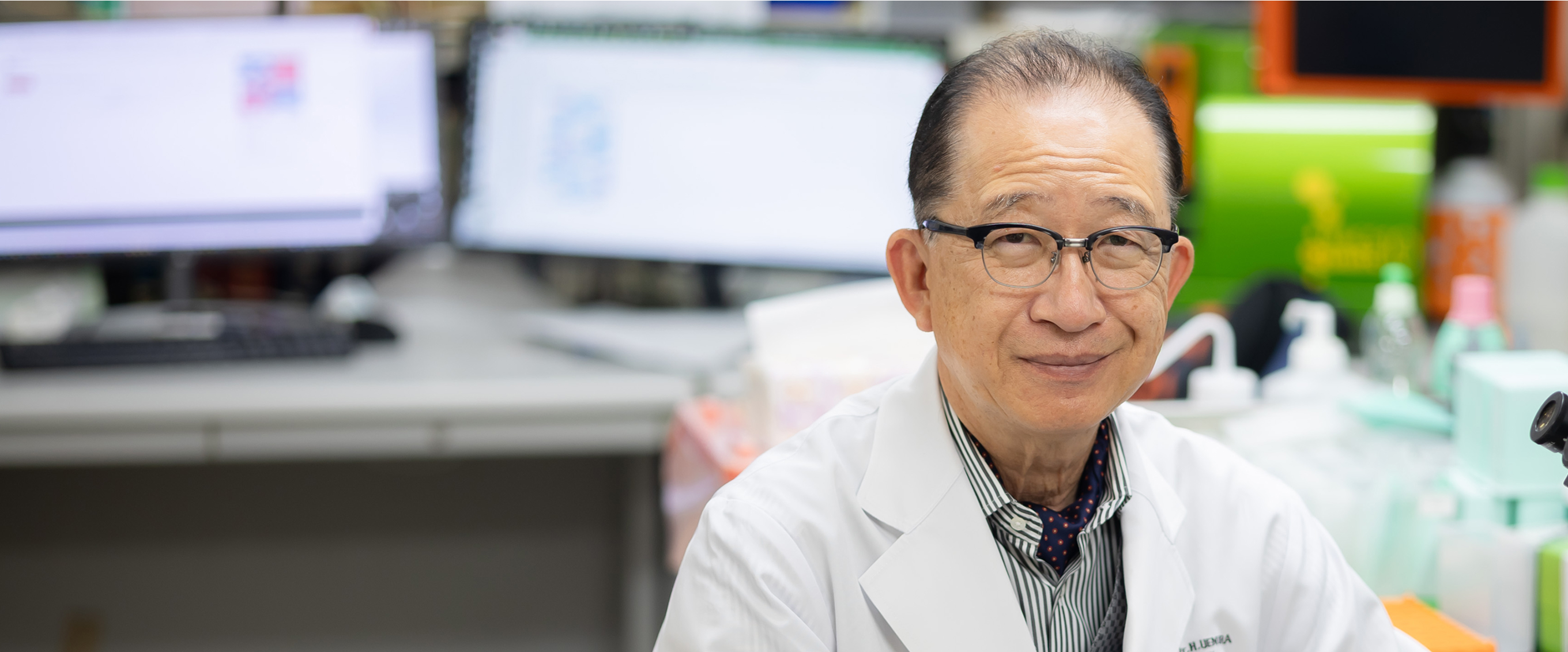
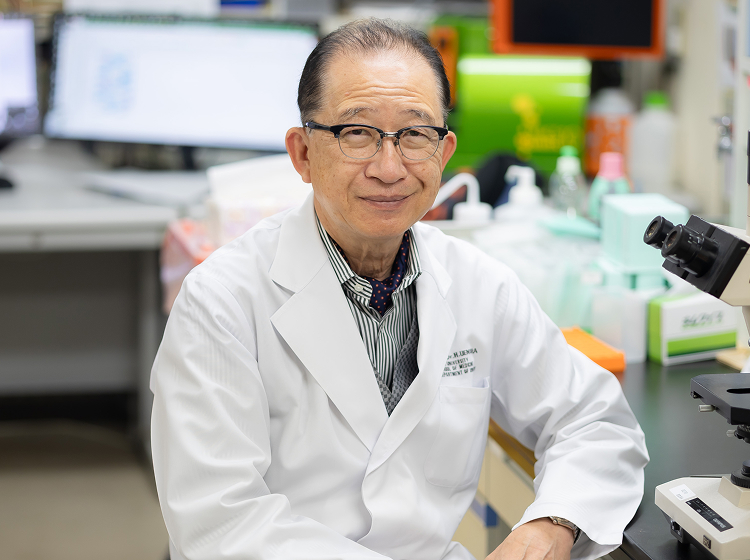
植村 天受
UEMURA Hirotsugu
名誉教授
Professor Emeritus
-
副病院長としての6年間で、病院運営や診療体制において大きな転機となった出来事や改革は何でしたか。
副院長の期間、病院長は消化器内科の工藤正敏教授でした。工藤院長は小職以上に多忙であったため、病院内の指示系統をスムーズにする必要があり、各部門が独立した部門としてではなく、事務・検査・看護・診療部門などをできるだけ一体化し風通しを良くすることに努めました。看護部長を副院長に抜擢し経営に参画していただいたのはこの時からです。 -
臨床研究センター長として、近畿大学附属病院の研究基盤整備や臨床試験推進にどのような役割を果たされましたか。
当時、近大病院には現在のような臨床試験を専門に取り扱う部門がありませんでした。IRBと医の倫理委員会の2つの委員会が最上層の部門で、現在のようにCOI委員会や事前審査委員会はなく、様々な問題が発生したと記憶しています。より透明性を高め、医師主導自主研究を迅速に審査し、治験を積極的に本院に取り入れるように部門や委員会の設立などに尽力いたしました。 -
臨床工学室長·人工透析部長として、人工透析医療や機器の導入·改善で特に印象に残っている取り組みはありますか。
まず、臨床工学部門を独立した組織として設立しました。当時の近大病院にはMEの数が少なくインフラの流れも一元化されておらず、ME数を増やし、医療機器・材料委員会を立ち上げました。また、透析室に関しては、今では腎臓内科が多くを担っていますが、当時は腎臓内科が設立されておらず、病院の諸事情から泌尿器科で100%担当するように言われ、ゴールデンウイークや年末年始の透析当番をするのに四苦八苦でした。 -
近畿大学泌尿器科において若手医師や大学院生を指導された中で、印象に残るエピソードや教訓はありますか。
若手医師や学生を指導するにあっては、「ほうれんそう:報告・連絡・相談」を最も重要な事項として教室内の風通しを良くしました。エピソードは数多くありましたが、最終的にほとんどがプライベートな内容となりました。 -
泌尿器科の医療技術や研究環境の変化を、2004年のご就任時と2024年のご退任時で比較すると、どのような点が最も変わったと感じますか?
医療技術において最も変化を遂げたのは、手術手技でしょう。開腹手術から腹腔鏡を用いた内視鏡手術、今では泌尿器科がんのほとんどがロボット手術になりました。次に大きな変革を遂げたのは癌薬物治療です。これは泌尿器科領域だけでないと思いますが、抗癌化学療法から分子標的治療、現在では免疫チェックポイント阻害薬を用いた複合免疫療法が標準となりました。 -
近畿大学附属病院でのチーム医療や他診療科との連携において、特に印象的だった事例を教えてください。
外科との共同手術が増えたことから、これまでであれば救命が困難な進行癌の患者を数症例救命でき、忘れ難い経験となった。 -
国際学会や海外での活動経験が、近畿大学での研究·診療にどのように活かされましたか。
大きな国際学会のメインホールで講演することで、それなりに第一人者として認められ、海外からの患者紹介(ロシア・・中国・アメリカなど)が数件あった。 -
近畿大学での在職期間を振り返って、特に誇りに思う業績や出来事は何ですか。
在職中に文科省科学研究費基盤研究(B)を6回も拝受し、ライフワークである泌尿器癌ワクチン開発の研究にて、国内特許3件取得し、うち一つはペプチドワクチン開発手法に関する包括的特許である。これ以外も含め国内外から競争的研究費を潤沢にいただき、種々の満足いく成果を公表できたこと。 -
これからの近畿大学医学部·附属病院の発展に向けて、後進や現役の医師·研究者に伝えたいメッセージをお願いします。
恕の心をもって診療にあたり、常に協力しえる将来性のある研究を目指してほしい。