Survey or Interview赤木 將男
「赤木ライン」の開発に成功
すべては患者のためにある
Having succeeded in developing the ‘Akagi Line,’we remain committed to putting patients first.

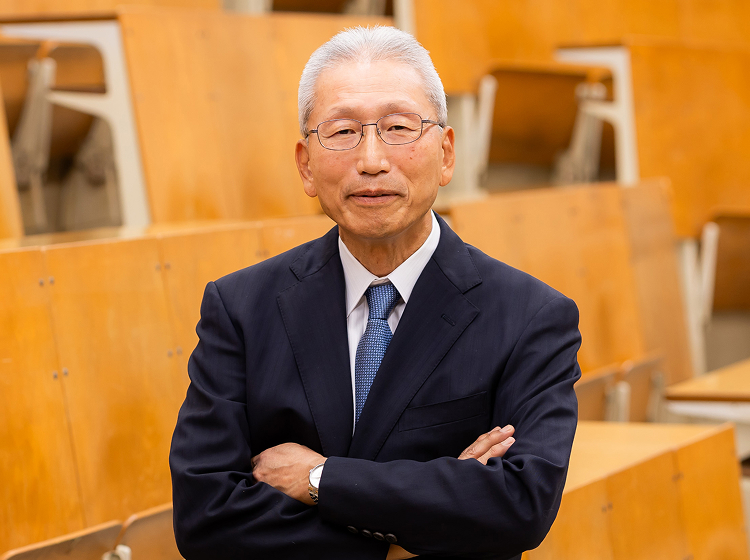
赤木 將男
AKAGI Masao
名誉教授
Professor Emeritus
-
ご専門の整形外科の中で、特に膝関節に焦点を当てたきっかけは何だったのでしょうか?
京都大学医学部附属病院に勤務していた頃にリウマチ班に所属していた。当時は関節リウマチで膝関節が悪くなり歩行困難となる患者が多かったことがきっかけ。 -
2001年に近畿大学医学部に着任された当時、整形外科の環境や課題はどのようなものでしたか?
人工関節手術が広く普及し始めた時代であったが、2次元的な手術計画やインプラント設置のみでは術後の成績不良や合併症が防ぎきれないことが課題であった。 -
「赤木ライン」が世界的に評価されるまでの研究プロセスや背景についてお聞かせください。
脛骨側インプラントの3次元的に正しい設置を実現するためには脛骨の前後方向を示す軸が必要であった。近畿大学着任後、京都大学で行った膝の3次元動態解析の結果を応用し「脛骨前後軸」を定義することに成功した。2002年に国内学会で公表し、2004年には英語論文として公表したが、2008年に海外の著名な整形外科医が私の「脛骨前後軸」を「赤木ライン」と名付けた論文を公表、世界的な評価を得ることになった。 -
人工膝関節置換術において、特にこだわってこられた点は何ですか?
また、それはどのような成果につながりましたか?可能な限り小さな侵襲で、正しい位置と角度にインプラントを設置することにこだわっている。手術成績の向上、インプラントの耐用性の向上、患者満足度の改善、合併症の減少につながった。 -
近畿大学医学部での教育や若手育成において、心がけてこられたことは何でしょうか?
臨床と研究において患者さんのためにひたむきに努力する自らの姿を見せること。 -
痛みを我慢しすぎないことの大切さをよく語られていますが、患者との信頼関係を築く上で意識されていたことはありますか?
痛みを我慢して生活していると徐々に歩行量が減少し、社会参加の機会を失う。その結果、全身的な心身の健康が損なわれることも多いことを説明している。その人がどのような人生を希望しているか話をよく聞き、適切な時期に治療を受けるよう勧めることを心がけている。 -
主任教授として約10年を超える間に、整形外科医療の中で最も変化した点は何ですか?
手術手技の安定と手術合併症の減少 -
ご自身の研究が医療現場で生かされていると感じる瞬間はどのようなときですか?
国内外の整形外科医に人工膝関節手術の際には脛骨参照軸として「赤木ライン」を用いていると言われるとき。また、現在もなお私の論文を引用した論文が数多く公表されていることを知るとき。 -
今後、人工関節治療の分野で期待される技術革新や課題について、展望をお聞かせください。
ロボットによる手術支援技術が不十分であることが課題である。今後、手術中の靭帯バランス評価をフィードバックしつつインプラント設置を自動的に調整、最適化する技術が開発されるであろう。また、個々の患者の術中データと術後成績の関連性についてのデータをAIが解析し、その結果をロボットに投入、個々の患者にとって最適なインプラント設置を自動で設計する技術が開発されるであろう。 -
若い整形外科医や医学生に伝えたい「整形外科医としての姿勢」とは何でしょうか?
「全ては患者のためにある」、それが医療というもの