Survey or Interview伊藤 浩行
高血圧続発症の病因研究、
テュートリアル教育導入を推進
Exploring causes of hypertension complications— advancing medical education through tutorial-based learning.

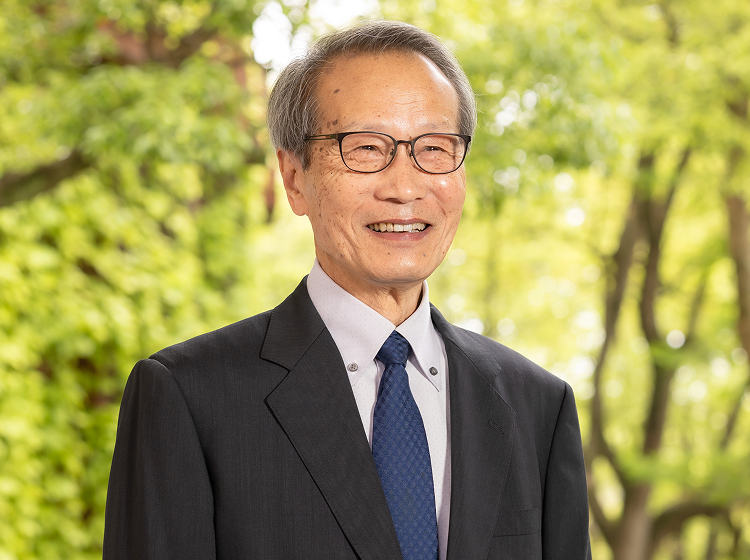
伊藤 浩行
ITO Hiroyuki
名誉教授
Professor Emeritus
- 近畿大学での在籍期間と歴任された役職・所属
- 1975年より2010年まで35年間
近畿大学講師(医学部第1病理講座)
近畿大学助教授(医学部第1病理講座)
近畿大学高血圧研究所教授
近畿大学付属病院病院病理部長・教授
近畿大学医学部教授(医学部第2病理講座)
近畿大学医学部教授(統合により病理学講座)
近畿大学附属看護専門学校校長
2010年より2015年まで6年間
近畿大学生物理工学部特任教授
-
専門分野と研究テーマ
専門分野:病理学(実験病理学・人体病理学)
研究テーマ:
- 弾性繊維(エラスチン)の生成と分解に関する研究。
弾性繊維は皮膚や動脈・肺などを始め、全身に広く分布する結合組織の一つで、ゴム状の弾力性により臓器・組織の機能に重要な役割を有しているが、老化や様々な疾患により破壊され、機能が大きく損なわれる。そこで主たる構成タンパク質であるエラスチンが生体内でどのように作られ、どのよう破壊されるか、また修復の方法はあるのか等について実験動物を用いて研究してきた。 - 高血圧による臓器障害とその予防に関する研究
高血圧症は日本人における最も多い疾患で、様々な臓器障害の重要なリスクファクターである。高血圧は種々の薬剤によりある程度治療することができるが、合併症・続発症を完全に予防することは未だ達成されていない。高血圧に関するモデル動物として、本学初代病理学教授岡本耕造先生によって開発された高血圧自然発症ラット(SHR)を用いて、脳障害・心筋障害・腎障害などにおける病因・病態を検索し、併せて治療に関する基礎的研究を行った。
- 弾性繊維(エラスチン)の生成と分解に関する研究。
-
教育・研究活動での記憶
教育:講師として医学部に赴任し、教授の指示に従って自身の経験を基に病理学の講義実習を担当した。カナダのマックマスター大学に留学した際、問題解決型テユートリアル教育(以下PBL)を体験し、衝撃を受けた。帰国後直ちに提言したが一言のもとに却下された。その後、橋本重雄教授・松尾理教授の下で教育改革に取り組み、よりよいカリキュラムの作成を模索した。全国的にも医学教育改革の機運が高まり、田中啓介学部長の強力なリーダーシップにより、遂にPBL テユートリアルシステムが導入された。長年の夢が現実となった瞬間で感慨ひとしをであった。また、開学以来延々と続けられて来た90分授業を60分に改める提案も何度か行ったが、その都度否定された。何度も検討を加えた結果、遂に多くの賛同を得ることができ、60分授業のカリキュラムの作成に漕ぎつけた。
研究:近畿大学に赴任してSHR とその開発者である岡本耕造教授と出会い、以後一貫してこの世界で類を見ないモデル動物を用いて高血圧続発症のpathogenesisに関する研究を行い、その原因としてフリーラジカルによる1種の炎症反応であることを明らかにすることができた。一方で、エラスチンに関する研究は当該タンパクが不溶性であるため遅々として進まず忸怩たる思いがあったが、現在では後継者により健康食品やbiomaterialへの応用へと進められている。 -
共同研究と国内外での交流
国内のエラスチン研究者に呼び掛けてエラスチン研究会を立ち上げ、幹事・代表幹事として共同研究の調整を行った。成果は「弾性繊維―構造と機能」にまとめられている。また、フィラデルフィア大学のRosenbloom教授、ワシントン大学のYu教授、マックマスター大学のDaniel教授・Kwan教授・Lee教授らとの交流によりエラスチンのみならず高血圧に関する実験的研究においても多くの教唆を得ることができた。 -
学生・若手教育で大切にしてきたこと
「教育における主役は学生である」という信念のもと、そのサポートを常に意識して教育活動を行ってきた。PBLはその最も適切な方法である。時には強力な指導も必要であるが、ともすれば押しつけ教育になりがちになることを自制しながら、「1を聞いて10を学ぶことができる学生」を理想として、自学自習の姿勢を大切にしてきた。
若手教育においては「常に疑問を持つこと」を強調した。未知の事柄に対する疑問のみならず、自身の得た結果に対しても疑問を持ち検証する姿勢を重視した。 -
研究・教育活動の継承
研究活動:後任教授との専門分野の違いにより、病理学教室での研究は継承されていないが、農学部や生物理工学部および鳥取大学工学部においてSHRを用いた研究やエラスチンに関する研究が継承されている。
教育:テユートリアルシステムや60分授業は現在も医学部カリキュラムの基本として継承されている。 -
在籍時の思い出
約40年の在籍中には幾多の思い出が溢れている。強いて挙げるならば、以下の4つは忘れえぬ思い出である。
- 医学部確立期:創設より第1期生の卒業まで医学部確立期は周辺地域の開発も相まって、狭山全体が沸き立つような活気に包まれていた。多くが経験不足で、試行錯誤の連続であったが、一つの目標に向かって協力し合えたことは幸せな経験であった。
- 留学:縁あってカナダのマックマスター大学へ留学した。異文化に触れたことは生活面のみならず、研究面でも教育面でも大きな転換点となった。この留学により以後の近畿大学での活動が可能になったと言っても過言ではない。
- 看護専門学校:校長を8年勤め、助産学科の創設や校舎の新設に携わり、よりよい看護師・助産師の養成を目指した。7年目・8年目に全員卒業・全員国試合格を達成し、教員共々喜びを分かち合ったのは懐かしい思い出である。
- 生物理工学部:医学部退任と同時に、新設された医用工学科に特任教授として赴任した。教員の中で医師は1人であったが、医学部の強力なサポートと教員の努力により軌道に乗せることができた。医学部創設時の情熱を再び感じることができたことは、晩年の大きな喜びであった。
-
期待と提言
創設50年・新キャンパスへの移転、当に再生の好機である。学生ファーストの教育・患者ファーストの診療とともに、常に研究マインドを維持し、教職員全員が一致して目指すべき方向を共有し、日本に冠たる医学部として成長発展することを切に期待している。