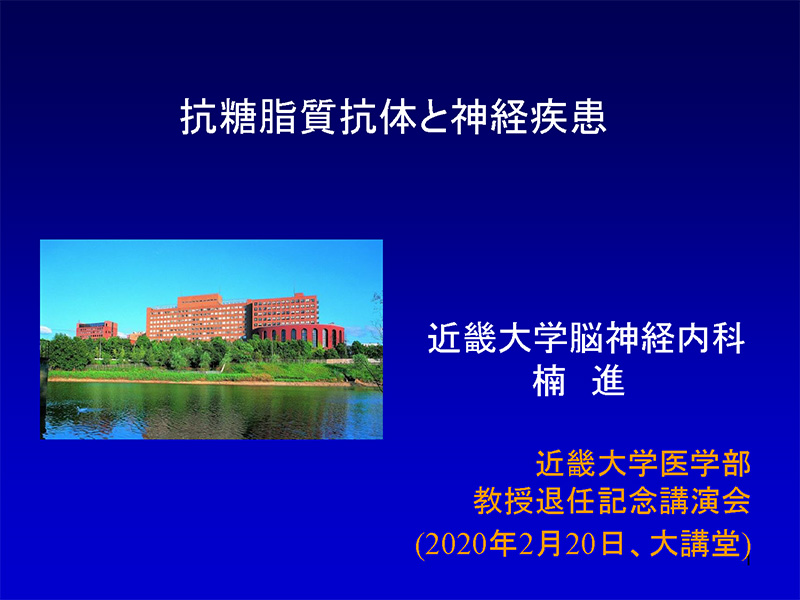Survey or Interview楠 進
論理性とひらめきを大切に
ガングリオシド抗体研究を貫く
Driven by logic and inspiration— advancing ganglioside antibody research with unwavering persistence.


楠 進
KUSUNOKI Susumu
名誉教授
Professor Emeritus
-
現在のご所属とご職名を教えてください。
虎の門病院分院・特別嘱託医 日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業プログラムスーパーバイザー(PS)、難病希少疾患疾患領域コーディネーター(DC) -
神経内科の中で、特にどのような疾患や病態に注力されてきましたか?
自己免疫によっておこる免疫性神経疾患が専門で、とくに先行感染(風邪、気管支炎や胃腸炎など)の後に麻痺が出現するギラン・バレー症候群や、その亜型で先行感染の後に眼球運動麻痺や運動失調をきたすフィッシャー症候群などの、免疫性末梢神経疾患の病態解明研究に注力してきました。 -
自己免疫性神経疾患の研究に取り組まれた動機を教えてください。
私の医学部卒業当時は、神経内科の研究は脳波・筋電図などの電気生理学的研究や病理学的研究が主体で、いまのような分子レベルの詳細な病態解明はほとんどすすんでいませんでした。その中で、自己免疫疾患については、既に重症筋無力症におけるアセチルコリン受容体抗体の発見や免疫調整療法の開発などもあり、病態解明や目に見える効果のある治療開発の手掛かりが得られやすいと考えていました。そうした時に、細胞表面のガングリオシドという分子が、自己免疫の標的となる可能性があるという講演を聞き、その新奇性に魅かれてガングリオシド抗体の研究をはじめました。東京大学医学部の生化学教室(永井克孝教授)で研究の手ほどきをうけましたが、ポジティブコントロールとして実験動物で作られたガングリオシド抗体の反応をELISA法でみたときに、うまく陽性反応の着色が得られたときはとても感激したことを覚えています。何か新しいことをみつけることができそうだという感覚が、自己免疫性神経疾患の研究をはじめた動機でした。 -
抗体検査の臨床応用に関する研究成果の中で、特に社会的インパクトが大きかったものは何でしょうか?
ギラン・バレー症候群の亜型のフィッシャー症候群に特異的に、かつ高い陽性率(約9割)でGQ1bガングリオシドに対する抗体が陽性となることを1992年に見出し、アメリカ神経学会誌(Annals of Neurology)に報告しました。これはフィッシャー症候群の有用な診断マーカーとなるとともに病態解明の手掛かりとなるものであり、国内外の研究者によって追試確認され、教科書や診断基準に記載され、医師国家試験にも出題されています。また有用な診断検査として、保険収載もされました。またGD1bというガングリオシドでウサギを免疫することにより、GD1bに対する抗体が産生されて四肢をうまく動かすことのできない運動失調性末梢神経障害をきたすことを報告しました。これはガングリオシド抗体による神経障害動物モデルの作成に世界ではじめて成功したものであり、ガングリオシド抗体が病気の原因であることを明確に示した研究でした。近畿大学着任後も抗体の研究を続けるとともに、全国から抗体検査の依頼を受けて、わが国の神経内科の日常診療に大きく貢献しました。これらの業績について、2017年に末梢神経についての国際学会であるPeripheral Nerve Societyから卓越した研究者に贈られるAlan J Gebhart賞を、また日本神経学会から日本神経学会賞を受賞しています。 -
近畿大学医学部に着任された経緯と、在職中に感じた印象深い出来事をお聞かせください。
私は、兵庫県の西宮に生まれて、小学校から高校までは京都で過ごしました。大学入学から東京でしたが、将来は関西に住むのもいいなと漠然と思っていました。そんなわけで、近畿大学医学部が神経内科の教授を公募していると聞き、是非この機会に近畿大学に赴任したいと思って応募しました。首尾よく着任することができ大変ありがたく思っています。近畿大学医学部では、京大、阪大、東北大などいろいろな大学出身の教授と親しくお付き合いしましたが、何となく出身大学ごとの雰囲気が感じられて興味深かったです。私は子供のころから高校野球が好きで、毎年熱心にみていましたが、1980年代のPL学園の強さはダントツでした。またPLの花火大会も全国的に有名でした。近畿大学医学部はその地域にあり、毎年PLの花火大会の時は交通渋滞が発生するので早く帰宅することが奨励されます。私もその時は早めに家に帰って、マンションのベランダから、花火鑑賞をしましたが、素晴らしい花火で、最後に空一面が明るくそまる様子は圧巻でした。コロナを機にその花火もなくなったようで寂しく思っています。 -
学生・研修医の教育において、大切にしてこられた信念や方針はありますか?
学生や研修医の教育においては、「論理性とひらめきをもつことが大切」と考え、そのように伝えてきました。医学部の学生も研修医も、医学という学問を実践しているわけですから論理的な思考を身につけなければいけません。論理的に考えることで、なすべきことが見えてくるわけです。一方で、医学という学問には、まだまだわからないことがたくさんあり、既存の知識で解決できないことだらけです。そこでは、論理的思考を超えた「ひらめき」が必要になることがあります。ただ、ひらめいたことは、論理的に検証することによって間違っている場合が少なくありません。その時は、そのひらめきは捨てなければいけません。そのようにして論理性とひらめきのバランスをとることが、学問、とくに医学においては重要と考えています。また、とくに研修医の教育では、それぞれの個人の適性に合った目標をもって研鑽をつんでほしいと考えてきました。研修医はもちろん医師の道を歩むわけですが、そこには研究者もあり、開業医も公衆衛生も・・・、それこそいろいろな方向があります。皆がある一定の方向性に向かうのではなく、自分に合った医師の人生を歩んでほしいと思っています。 -
多発性硬化症・視神経脊髄炎などの中枢神経疾患への研究成果と今後の展望について教えてください。
私は2008年から2014年まで6年間、厚生労働省の免疫性神経疾患調査研究班の研究代表者(班長)をつとめました。この研究班は、中枢神経・末梢神経・筋の領域の自己免疫性の病態による疾患を扱う大きな研究班です。その間、2009年に兵庫県の淡路島で、当時アクアポリン4抗体が発見されて病態解明がすすみつつあった視神経脊髄炎についての国際シンポジウムを開催して、日本の研究者と欧米の研究者の交流を深めました。また視神経脊髄炎の全国調査を実施して2018年に英文誌に報告しました。また宮本勝一准教授(現和歌山県立医大教授)との共同研究で、多発性硬化症の動物モデルとされる実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)について、糖鎖を含む分子(糖脂質やプロテオグリカン)の病態との関連という観点から多くの論文を発表しました。さらにミエリンに局在する糖脂質のガラクトセレブロシドに対する抗体が、マイコプラズマ肺炎後のギラン・バレー症候群だけでなく脳脊髄炎にもみられることを報告しています。現在、中枢神経疾患を含む免疫性疾患には、多数の分子標的薬が開発されていますが、今後さらに分子レベルの病態解明に基づく新規治療法の開発がすすむと期待しています。 -
近畿大学での研究を通じて、どのような国際的なネットワークや共同研究が築かれましたか?
近畿大学でのガングリオシド抗体研究を行う中で、英国のグラスゴー大学のWillison教授との交流がすすみました。私が会長をつとめた日本神経免疫学会や日本神経学会にも招待講演をお願いするとともに、医局員の桑原基講師がグラスゴー大学に留学して、彼らの開発した新しい抗体測定法を学んで日本で応用して、複数の重要な論文を発表しました。またオランダのエラスムス大学のJacobs教授とは、ギラン・バレー症候群の疫学研究を通じて交流し、医局員の山岸裕子医師がエラスムス大学に短期滞在して、疫学的手法を学び論文を発表しました。私は、オランダが中心に行われているギラン・バレー症候群の国際共同研究であるIGOSのSteering Committeeの一員として参加しました。また炎症性ニューロパチーコンソーシアムの理事もつとめました。多発性硬化症や視神経脊髄炎の権威である米国Mayo ClinicのWeinshenker教授とも、NMO国際シンポジウムを通じて知己を得て、Mayo Clinicを訪問して講演する機会を得ました。その他にもドイツ、韓国、バングラデシュなど多くの国の研究者と共同研究や情報交換を行いました。このように近畿大学での研究を通じて、免疫性神経疾患全般に、多くの国際的な交流や共同研究を行うことができました。 -
退官後も継続されている活動や研究があれば教えてください。
近畿大学主任教授を退任後も、医局の免疫性神経疾患の研究グループとは、定期的に研究打ち合わせを行っています。近畿大学を中心とした多施設共同研究で「GD1a抗体がギラン・バレー症候群の予後不良と関連する」という論文を発表した際には、プレス発表をして科学新聞その他に掲載されました。また私自身は、現在日本医療研究開発機構(AMED)の難治性疾患実用化研究事業のプログラムスーパーバイザーおよび難病希少疾患領域の疾患領域コーディネーターとして、神経疾患を含めた難病に関係するAMEDが支援する研究(がん難病全ゲノム解析研究、未診断疾患イニシアティブ、難病プラットフォーム等多数)の進捗管理や評価を行っています。 -
今後の神経内科学の発展に向けて、後進に期待すること・メッセージをお願いします。
いま神経内科の病態解明研究は学問的にもホットな領域となり、常に新しい研究手法が導入されてきています。そうした中で、研究には医師だけでなく理学部や農学部・薬学部など他学部の研究者が続々と参入しています。それは大変よいことだと思うのですが、一方で臨床医は日々の診療に追われて研究の時間がとれなくなっている状況だと思います。AMED関係の仕事をしていて、やはり病気を知っている臨床医が研究に従事することが必要だと実感するようになりました。若い先生方は日常の診療を「こなす」だけでなく、何か新しいことがないか、自身の触覚をはたらかせて見出そうとしてください。そして、論理性とひらめきを大切にしながら、国際的な視野をもって、神経内科学をさらに発展させていってください。大いに期待しています。