Survey or Interview奥野 清隆
外科の厳しさは同時にやりがい
5年後の自分を見据えて
The rigor of surgery brings challenge and fulfillment— shaping who you’ll be five years from now.
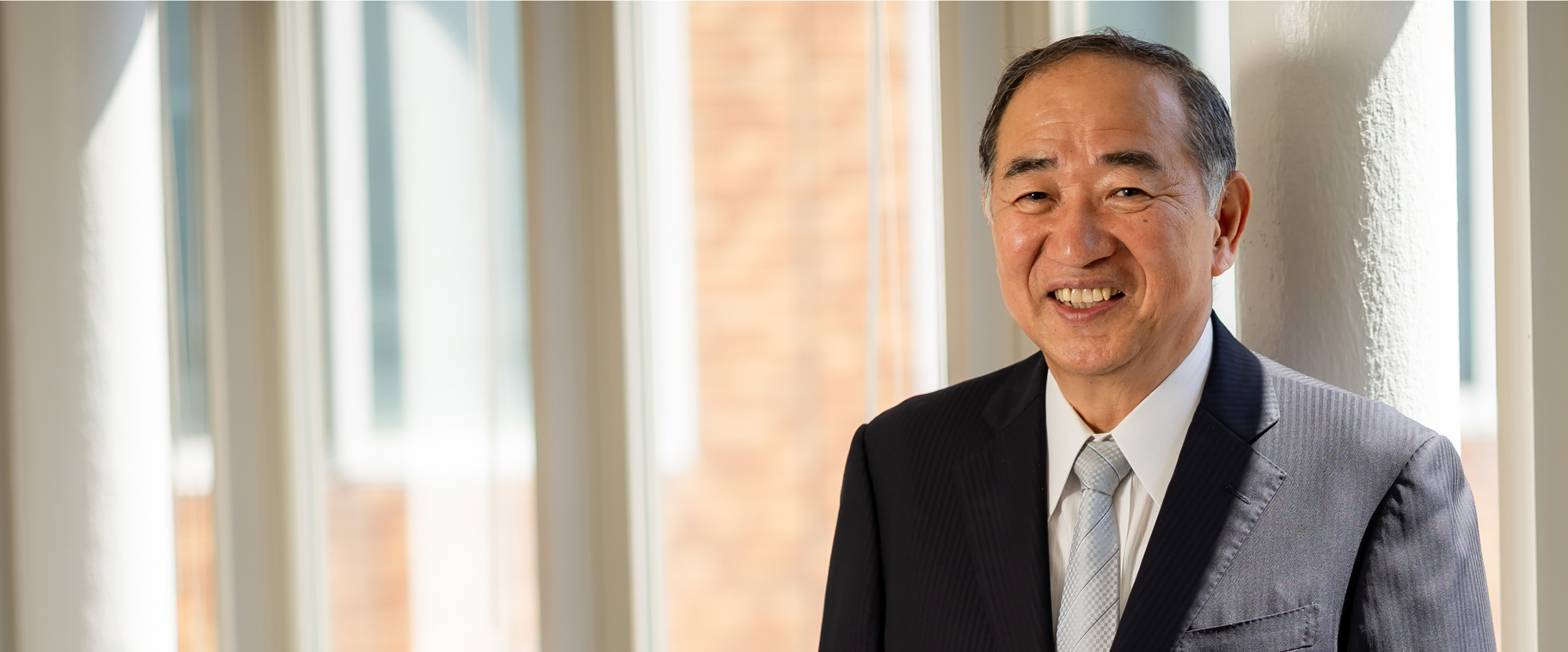

奥野 清隆
OKUNO Kiyotaka
名誉教授
Professor Emeritus
-
近畿大学医学部および附属病院におけるご経歴を、特に印象深かった役職・活動も交えてお聞かせください。
病院長時代には病院事務部から累積赤字の改善を求められ、加えて救命救急センター跡地利用、エレベーター問題(絶対数不足、患者さんと職員の混合利用)、駐車場問題(他施設と比較して高額)、支払いのクレジットカード利用等、問題山積であった。全面移転を控えたうえでそれらの仕分けを事務部と共同して行ったことが印象深い。 -
腫瘍外科・下部消化管外科の分野で、先生がキャリアを通じて特に力を注がれたテーマ、アプローチについてご紹介ください。
- 大腸癌肝転移に対する集学的治療(肝切除、免疫化学肝動注、全身化学療法)の開発とそれによる生存率の改善
- 下部直腸癌に対する究極の肛門温存手術を2000年初頭より取り組み、括約筋温存術式の確立に寄与
- 中村祐輔教授らとの共同研究で行ったオンコアンチゲンペプチドを用いた再発大腸癌に対する免疫療法、等
-
病院長やライフサイエンス研究所所長といったリーダー職に就かれた中で、実現できた改革・挑戦的な取り組みがあれば教えてください。
病院長時代に救命救急センター跡に新規手術室の増築を執行したこと。当時、コンサル会社(BCG)は数年後の移転を控えて数億円の出費には反対との立場だったが結果的には病院移転計画が遅れ、その間の手術増による病院収益増加に寄与出来た。
一方、達成出来なかったことは- クレジットカード払い
- 駐車料金の低額化
-
米国での研究経験や、国際学会でのご活動が日本の医療現場にもたらした影響についてお聞かせください。
帰国直前にヒトメラノーマ癌抗原(p97)の共同研究に参画したが、もう少し時間的余裕があれば、「ヒトがん特異抗原の同定」に深く介入出来たのに、と残念に思う。しかしながら所詮人生には自分の努力だけでは打開出来ないタイミングや出会いがある。米国留学は他の雑音から隔絶して研究に打ち込める貴重な経験だった。 -
教育者として、若手外科医や医学生の育成において大切にしてこられた信念・工夫があれば教えてください。
患者さんの生命に直結する外科手術の難しさ、厳しさ、それは同時に外科医の充実感、達成感でもあるが、そういった「外科の楽しさ、やりがい」を若手外科医、医学生に伝えたいと考えてきた。しかしながら自分に染み付いた「昭和の価値観」は如何ともしがたく、個人のライフスタイルを重視する若手外科医に十分伝わったかどうかは不明。 -
附属病院の医療チームの中で築かれた文化や、今でも心に残る医療現場でのエピソードがあればご紹介ください。
1977年和医大卒業以来、阪大癌研、米国ワシントン大学 (シアトル) 時代を除けば、ほとんど近大医学部、附属病院で過ごしたため近大の文化しか知らない。入局当時は各医局ごとに出身大学(阪大、京大、東北大、日大)独自の文化が色濃く持ち込まれていて教室行事や医局方針など、とても興味深かった。 -
これからの近畿大学医学部・附属病院に期待される役割、医療の未来像についてメッセージをお願いします。
医学部50周年を迎え、もはや新設医大ではなく、診療、研究ともに日本の中枢を担う医学部に成長したことを嬉しく、誇らしく思う。さらにはこれからの近大医学部を担う若手医師、医学部生には未来医療を念頭に積極的に新しい領域を開拓してほしいと願う。 -
これから医療界に羽ばたく若手医師・研究者・学生たちへのメッセージをお願いいたします。
学生時代はしっかり勉強すること、基礎医学(解剖学、病理学、薬理学、免疫学)の知識は将来、何科に進んでも役に立つ。医師になったら常に「5年後の自分」を見据えてそれぞれの科で楽しく努力してほしい。「忙しさと楽しさは相反するものではない」(塩﨑学長の教室心得より) -
その他、50周年史にぜひ記しておきたいエピソード、言葉などがありましたらご自由にお書きください。
- 開院当時、病院周辺は更地ばかりで、ほとんど住宅がなかった、
- 金剛駅からの南海バスが病院前のスペースでUターンして帰っていった、
- ガスタンク下にテント村が出来てそこで何とか夜食にありつけた(泉ヶ丘パンジョまで行けばもちろん食事は出来た)等々。50年前の医学部、附属病院周辺は正に「陸の孤島」だった。