Survey or Interview川田 暁
光老化皮膚研究を拓き
研究マインドを持った臨床家育成
Pioneering research on photoaged skin— fostering clinicians with a research mindset.


川田 暁
KAWADA Akira
名誉教授
Professor Emeritus
-
近畿大学でのご経歴の中で、特に印象に残っている出来事や研究は何ですか?
1999年4月に近畿大学医学部皮膚科助教授に就任し、その後教授を経て、2021年3月に定年退職するまでの22年間近畿大学に勤務させていただきました。一番印象に残っているのは一緒に仕事をした方々との「出会い」です。上司の故手塚 正名誉教授、医局の同僚の方々、外来・病棟の看護師や事務の方々、医学部・病院の事務の方々、医局秘書の方々、附属看護学校の先生方や事務の方々、など数えきれないほどの人達との出会いがあり、皆さんに助けていただきました。それらの方々のおかげで、皮膚科学教室の運営を定年までやりとげることができました。改めて深謝申し上げます。
研究面では、長年継続してきた光老化の予防の研究での実績が評価され、WHOのIARC (International Agency for Research on Cancer) の専門家による会議 (2000年4月リヨン、フランス) に参加し、本 (図1、2) の作成に関わることができたことです。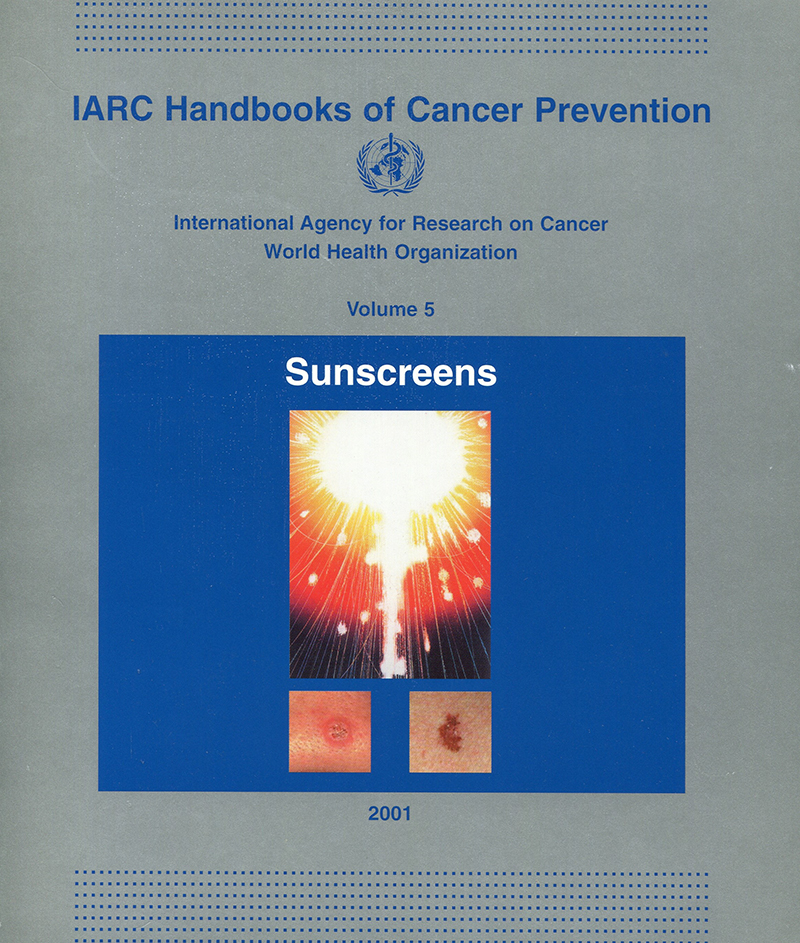
図1.IARC Handbooks of Cancer Prevention Vol. 5 Sunscreens の表紙 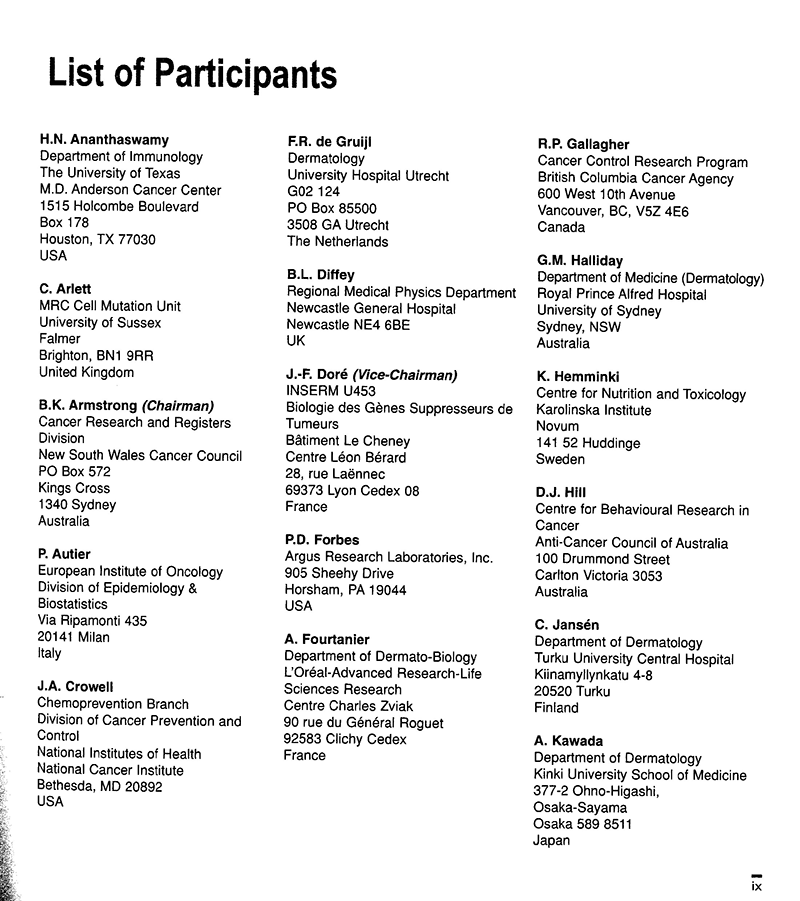
図2.参加者リスト -
光生物学・光老化研究に取り組まれた動機や、その意義について教えてください。
私が光生物学の研究を始めたのは東京医科歯科大学 (現東京科学大学) 時代です。故佐藤吉昭先生の御指導の下、日本人のスキンタイプについて検討しました。スキンタイプというのはヒト皮膚の紫外線感受性 (サンバーンとサンタン) による分類を言います。当時白人のスキンタイプはありましたが、アジア人のスキンタイプはありませんでした。そこで佐藤先生と私とで、日本人の紫外線感受性を検討して「日本人のスキンタイプ分類」として発表しました。日本人の紫外線感受性が白人のそれとは異なることを初めて明らかにした、きわめて意義深いものであったと考えています。
光老化とは紫外線を長期間継続して当たると生じる皮膚の変化を言います。シミ・シワが増え、皮膚癌も生じやすくなります。それを予防するためには、サンスクリーン剤を含む紫外線防御が大切です。そこで東京医科歯科大学と防衛医大時代に、サンスクリーン剤による紫外線防御について多くの基礎的研究を行いました。これらの研究は香粧品業界ではありましたが、皮膚科領域では私達だけの独自のものであり、多くの健常人や患者さんにとってきわめて重要であったと考えています。
手塚先生の専門の1つとしてレーザー療法があります。手塚先生は当時日本のレーザー治療の第一人者でいらっしゃいました。私は助教授として近大皮膚科に着任してから、ご指導を賜り自分の専門の1つとして積極的に取り入れてきました。そしてこのレーザー治療を光老化皮膚の症状であるシミやシワの治療に導入し、高い効果と安全性を明らかにして多くの英文誌に発表しました。すなわち近大に着任するまでは光老化の予防を中心に研究していたのですが、近大からは光老化の治療に注力することになりました。当時大学病院でこのような治療をする所はなく、大きな注目を浴びました。 -
主任教授として医局を率いる上で苦労された点と、それをどう乗り越えられたかを教えてください。
2004年に主任教授に就任した時には多くの中堅の医局員が開業などで医局を辞めていきました。そのため医局員の人数が極端に減少し、かつ若手の医師中心となりました。このような状況で大学病院の皮膚科としての高い質と量の診療を維持することは大変困難でした。私自身が率先して働く事と、若手医師と密なコミュニケーションをとる事を心がけました。具体的には週6日のうち5日間初診担当医となり、初診患者さんに加えて再診患者さんの診察をしました。病棟へは週1日の教授回診に加えて、ほぼ毎日主治医とともに入院患者さんを個別に診察し治療方針を検討し決定しました。その後毎年複数人の入局者があったため、何とか定年までの17年間充実した診療を成し遂げることができたと思っています。 -
近畿大学附属看護専門学校 校長時代の思い出や、教育へのこだわりについてお聞かせください。
2012年に近畿大学附属看護専門学校の校長を拝命し、2020年までの8年間務めました。看護専門学校の使命は、患者さんに寄り添う暖かい心を持った、質の高い看護師を育て、高い国家試験合格率を目指すことだと考えました。私自身の役割は、学生が勉強に励むことが出来る環境を整えることと、看護専門学校の教員や事務の方々が働きやすい環境を整えることでした。8年間という比較的長期間、大きなアクシデントもなく務めることができてほっとしています。多くの会議や式典に参加させていただき、それを通じて教員や事務の方々と交流できたことも楽しい思い出です。また校長と同時に近畿大学の評議員も拝命し、評議員会の一員として大学の運営に参加させていただきました。 -
乾癬学会・美容皮膚科学会などの学会運営に携わって得られた学びは何でしたか?
まず乾癬学会ですが、先代の近大皮膚科教授の手塚 正先生が1999年~2003年に理事長となられ、その時に事務局長を務めました。乾癬学会というのは「乾癬」という1つの疾患だけを対象とするきわめてユニークな学会です。乾癬というのは皮膚科領域の中でもメジャーな疾患ですし、それを扱う基礎研究も極めてレベルが高く、また様々な新薬が開発されてきました。私は2004年に評議員、2005年に理事となり、2014年~2018年に理事長を務めました。理事長時代には学会としてのエビデンスを発信するために、学会主導の疫学調査を多数行い、英文誌に発表しました。また2011年には年次学術大会 (図3) を会長として開催しました。
次に美容皮膚科学会のお話をします。光老化研究の所で触れたように、レーザー治療はシミやシワの治療に対して高い効果と安全性が明らかになりました。この頃から皮膚科領域では美容皮膚科に対する関心が高まり、多くの皮膚科医や形成外科医が専門とするようになりました。それにつれて美容皮膚科学会は会員数が増加し、大きな注目を得るようになりました。私は2011年に本学会の評議員、2014年に理事となり、2017年~2019年に理事長を務めました。「美容皮膚科」という領域が学術的に適切であり、かつ患者さんに有益となるように注力しました。また2015年には年次学術大会 (図4) を会長として開催しました。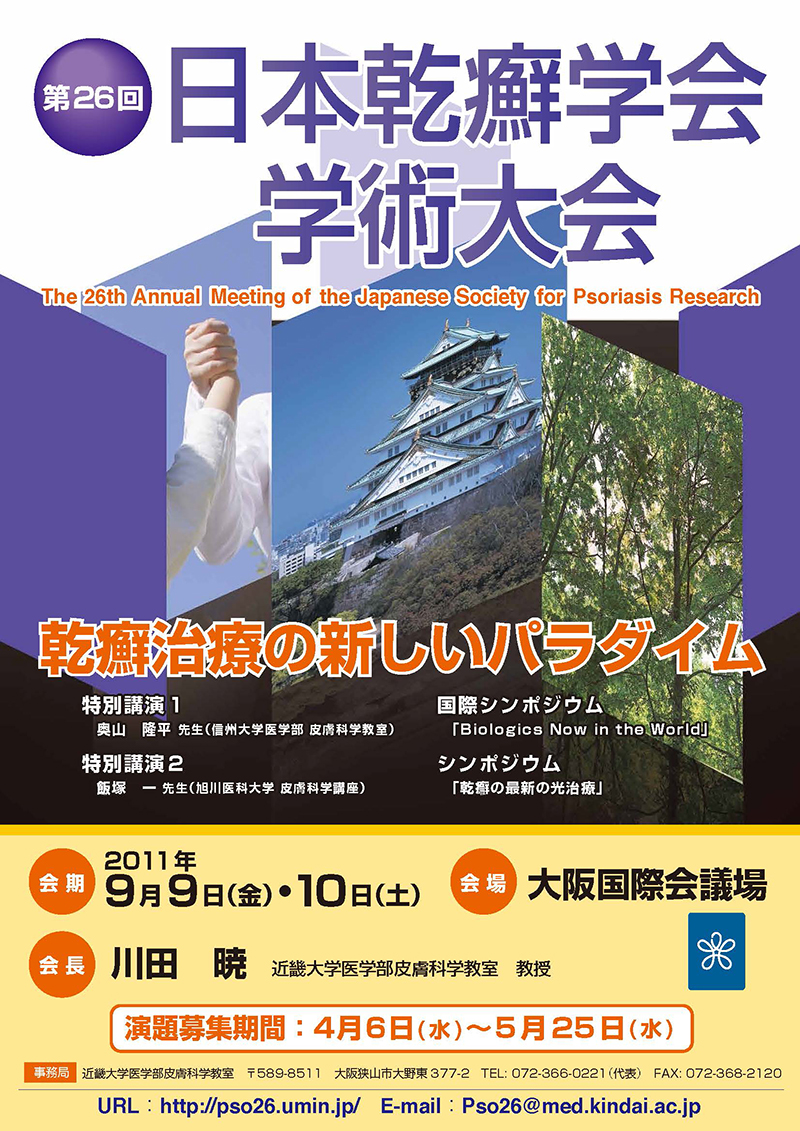
図3.第26回日本乾癬学会学術大会のポスター 
図4.第33回日本美容皮膚科学会総会・学術大会のポスター -
『皮膚の科学』編集長としてのご経験で、皮膚科医学の発信における課題と意義を教えてください。
「皮膚の科学」という雑誌 (図5) は、2001年に日本皮膚科学会大阪地方会の機関誌の「皮膚」(1959年創刊) と京滋地方会の「皮膚科紀要」 (1923年創刊) が合併して出来た歴史のある学会機関誌です。皮膚科領域の総説、研究論文、症例報告、学会抄録、などによって構成されています。私は2006年から本誌の編集委員、2013年に編集委員長を務めました。医学的に質が高く、かつ読者 (皮膚科医または皮膚科専門医) に有益な雑誌になるように編集委員の方々と努力しました。現在でも発行は継続していますし、評価は高いと思います。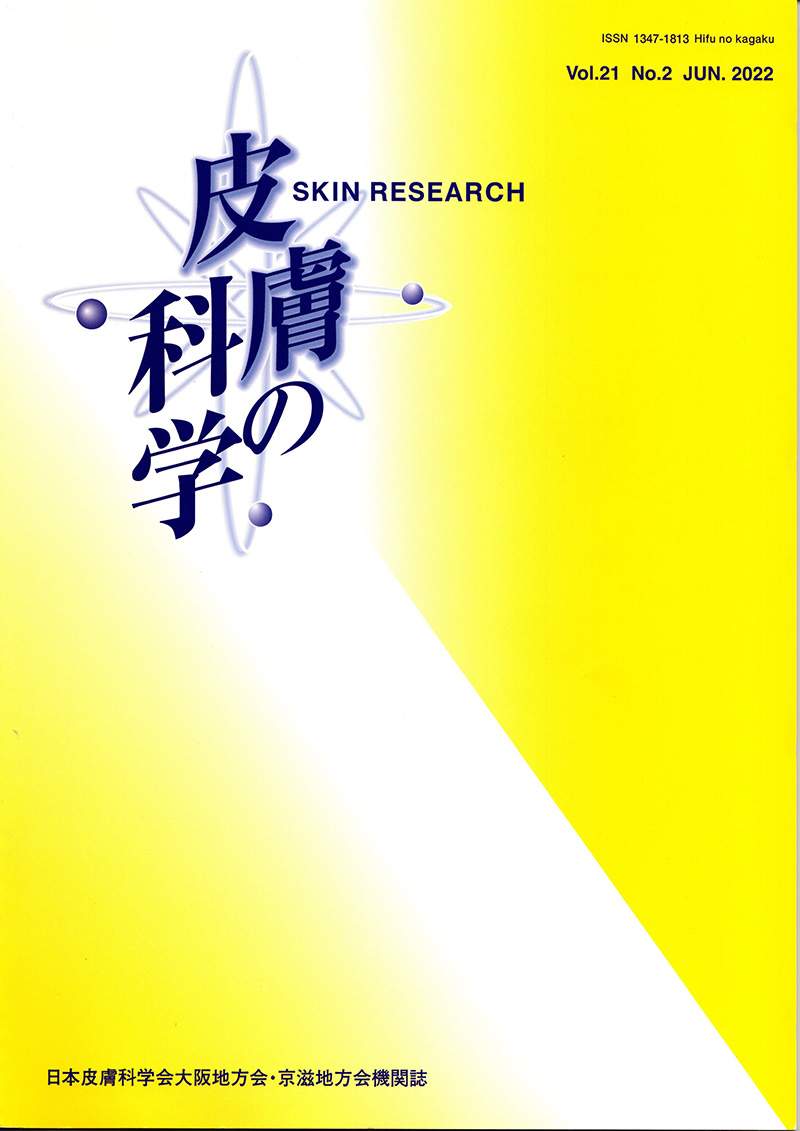
図5.雑誌「皮膚の科学」の表紙 -
基礎研究と臨床研究のバランスをどのように保たれてきたのか、その工夫を教えてください。
近畿大学附属病院を含めて4つの大学病院に約38年間勤務しました。その間は physician scientist (研究マインドをもった臨床家) を目標にしました。臨床家であることを基本にして、患者さんの診療を大切にしました。その上で臨床と関連のあるテーマの研究を進めていきました。またその研究から得られた成果を臨床にフィードバックしました。
教授になってからは physician scientist としての医局員を育成することを目標としました。まず基本として皮膚科専門医としての診断・治療能力を取得してもらいました。その上で私自身の専門である乾癬や美容皮膚科、大磯准教授の色素異常症と円形脱毛症においても積極的に研究してもらいました。また大学院生については、近大医学部免疫学宮澤教授や近大薬学部化学療法学中山教授の研究室に出向して研究していただき学位を取得してもらいました。 -
海外留学(UCSF)や国際学会への参加が現在の研究・教育にどう影響を与えたか教えてください。
1990年-1992年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校に留学しました。アメリカの研究スタイルを経験できたこと、生活を通してアメリカの文化に触れることができたこと、研究室内外の多くの友人ができたこと、などが良かった点です。皮膚科の臨床・研究における、アメリカと日本の違いと共通点が理解できました。日本の良い点を伸ばして悪い点を改良していけば、素晴らしい皮膚科になると思いました。最近海外留学する人が減っているのはとても残念に思います。
国際学会には医局員と一緒に積極的に参加し、発表するようにしていました。アメリカ皮膚科学会、ヨーロッパ皮膚科学会、アジア皮膚科学会、世界皮膚科学会にはなるべく毎年学会発表するようにしていました。外国の皮膚科医や研究者と交流し、さらに異文化を体感できてとても良かったと思います。 -
医師・研究者として、後進へのメッセージをお願いいたします。
近畿大学は伝統にしばられず自由闊達な学風があり、努力さえすれば医師や研究者として大きく成長できます。病院のスタッフは優秀で、レベルはとても高く、規模も南大阪では最大です。また医学部以外の他の学部との交流もさかんですので、幅広い研究も可能です。このように素晴らしい環境が用意されていますので、是非頑張っていただきたいと思います。 -
今後、皮膚科領域で特に注目すべき研究テーマや社会的課題は何だとお考えですか?
皮膚癌の中でも悪性度の高い悪性黒色腫 (メラノーマ) 、悪性リンパ腫の新規治療法の開発や予防が発展すると思います。そのほか、アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬などの炎症性疾患に対しては新しい治療法が続々と開発されており、今後もこの傾向が続くと思います。社会的課題としては、患者さんがとても困っているのに良い治療法がなかった疾患である、多汗症や酒さに対してもっと基礎研究や新薬の開発を進める事だと思います。