Survey or Interview伊木 雅之
長期追跡コホート研究を成し遂げ
骨粗鬆症・骨折予防に挑む
Through long-term cohort studies— advancing the prevention of osteoporosis and fractures.
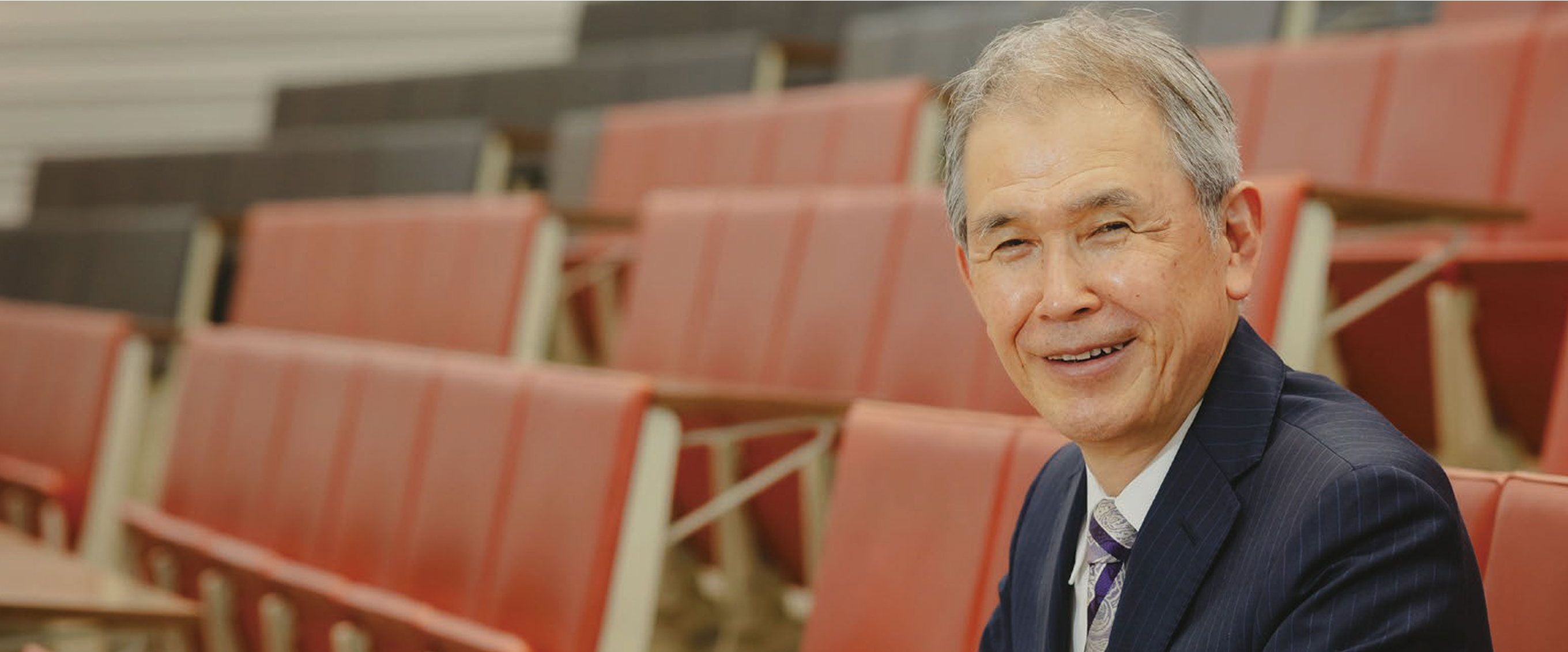

伊木 雅之
IKI Masayuki
名誉教授
Professor Emeritus
- 近畿大学での在籍期間と歴任された役職・所属
- 1997年近畿大学医学部公衆衛生学主任教授。
2014年~2018年近畿大学医学部長。
2018年近畿大学評議員、近畿大学ライフサイエンス研究所長、近畿大学医学部図書館長。
2022年定年退任し、近畿大学名誉教授、医学部公衆衛生学客員教授。
-
ご専門分野と、特に注力された研究テーマをご紹介ください。
疫学、予防医学。中でも骨粗鬆症とそれによる骨折予防のための疫学研究に力を入れてきた。骨粗鬆症は有病者数1300万人を超え、無症状の内に進行し、骨折を引き起こす。ひと度骨折すればADLとQOLを低下させ、要介護の主要な原因となっている。その変容可能なリスク要因を明らかにするため、2つのコホート研究を立ち上げた。一つは女性を対象にしたJapanese Population-based Osteoporosis Study(JPOS)研究で、他方は男性を対象にしたFujiwara-kyo Osteoporosis Risk in Men (FORMEN) 研究である。JPOS研究は日本で最長の追跡期間25年を誇り、FORMEN研究は男性の大規模コホートとしては唯一のもので、15年追跡が完了している。 -
近畿大学医学部での教育・研究活動で特に記憶に残っている成果や取り組みはありますか?
教授就任初年度の12月に「医学教育者のためのワークショップ」に参加するようにと医学部長からご下命を受けた。研修所に6日間缶詰になり、最新の医学教育理論に基づく、カリキュラム編成について学んだ。研修所は富士山の樹海の只中にあり、逃げ出すのは命がけと思われ、諦めた。しかし、学んだことは大変貴重で、私のその後の医学教育を理論的に支えるものになった。教育には、大学レベル、学部レベル、教科レベル、個々の講義レベルのそれぞれに目標があり、目標には一般教育目標(GIO)と個別的行動目標(SBO)がある。それを決めて、その目標が達成できるように授業、教科を編成する。それによって目標が達成できたかどうかを調べて評価する。この方法に従って3年目には公衆衛生学のカリキュラムを一新した。以後、修正を繰り返し、学生から高く評価されるようになったのは良い思い出である。 -
共同研究や疫学的コホート研究などで印象深かった経験をお聞かせください。
女性の骨粗鬆症に関するコホート研究JPOS研究は1996年に初回調査が実施された。北は北海道、南は沖縄まで全国に配置した7市町の女性住民から計4550人を無作為抽出して調査対象とする研究で、車載型二重エネルギーX線吸収法を使って骨密度測定や脊椎イメージングを行った。私は研究事務局長だったので、全ての地域を訪問して、調査の説明をし、調査員教育にあたり、1996年はこれで明け暮れた。対象者は無作為抽出だったにも関わらず、現地保健部門の方の絶大な協力で受診率は80%を超え、調査は大成功だった。その後、7市町の内、5市町について追跡調査を実施し、25年続いている。長期に続けられた一番の要因は現地保健部門のスタッフとの信頼関係だ。首長が変わるとこのような「余計な」事業は引き継がれないのが通例だが、それを乗り越えられたのは現地スタッフの皆さんの支えがあったればこそだった。しかし、初回の調査に比べると現地に求める仕事量は格段に少なくなった。長年お付き合いしていると、市町村には人的余裕はなくなっていることを痛感する。私たちに関わりのない分野を含め、行政の弱体化を危惧している。一方、コホート研究はあまたあるが、10年を超えて対象者の80%を追跡できている研究は少ない。追跡10年の論文が出たころから、海外からの共同研究のオファーが舞い込むようになった。長年続けているといろいろ研究の間口が広がって終わりが見えなくなって、引退の身としては苦慮している。 -
在籍中の学生・若手教員との関わりや、後進育成において
大切にしていたことを教えてください。教室運営にあたっては以下の3点を基本とした。①まずは学生教育。大学は教育機関である。いくら忙しくても教育で手を抜くことは許さない。②わずかな教室員なので、必要な時は一致協力し、1+1が3になるように仕事をしよう。③人を対象にする研究では結果を論文化することは協力者への義務である。原著論文をコツコツ書いて協力に報いよう。 -
ご自身の研究が近畿大学医学部に与えた影響について
お聞かせください。日本の骨粗鬆症コホート研究と言えば、女性を対象にしたJPOS研究、男性を対象としたFORMEN研究が挙げられるようになった。いずれも私が研究代表者を務めたもので、近畿大学発のコホート研究であることから、近畿大学の評価を高めたと考えている。 -
学内行政(学部長、図書館長など)において取り組まれたことで、
記憶に残るものがあれば教えてください。Q2で述べたように、公衆衛生学の教育は具体的な行動目標を達成できるかどうかを評価軸にして組み上げたもので、よくできたカリキュラムだと自負していた。しかし、私が医学部長の時、医学教育界に黒船が襲来した。医学教育分野別評価である。この評価を受け、国際機関が定める基準を満たさないと、卒業生がアメリカ合衆国の医師国家試験(ECFMG)の受験資格を失うという。近畿大学を卒業してECFMGを受けられないというようなことは許されない。当然受審したわけだが、評価基準を見て驚いた。その包括性と詳細さもさることながら、目標達成型のカリキュラムにテュートリアルを大胆に導入した少人数参加型の教育システムは、導入当初は医学教育改革の先頭を走っていたわけだが、それから十数年が経ち、世界の医学教育がアウトカム基盤型に進化していたにもかかわらず、本医学部は大きく取り残されていたのだ。そこから現状を把握し、評価し、具体的対応策をあげ、その実施計画を作成する、その作業を各評価項目について行い、自己点検評価報告書を書き上げた。それに対する評価機構からの指摘事項に回答し、2017年10月に実地審査を受けた。厳しい質問が相次いだが、無事、審査に合格することができた。カリキュラムはかくも多方面から検討しなければならないものかと幾度も思い知らされた。 -
近畿大学医学部・病院の今後について。
医学部も病院も泉ヶ丘でまっさらになるわけですから、心機一転、頑張ってくださるに違いないと信じています。私からの提言などはありません。でも、大きな期待はしています。次の10年、近畿大学医学部は研究面においても、診療面においても、教育面においても大きな飛躍を遂げられるでしょう。それを見守ることを楽しみにして生きたいと思っています。