Survey or Interview佐賀 俊彦
近大心臓外科として新しい課題に
絶えず先進的に取り組む
Kindai Cardiac Surgery— continuously taking on new challenges with a pioneering spirit.

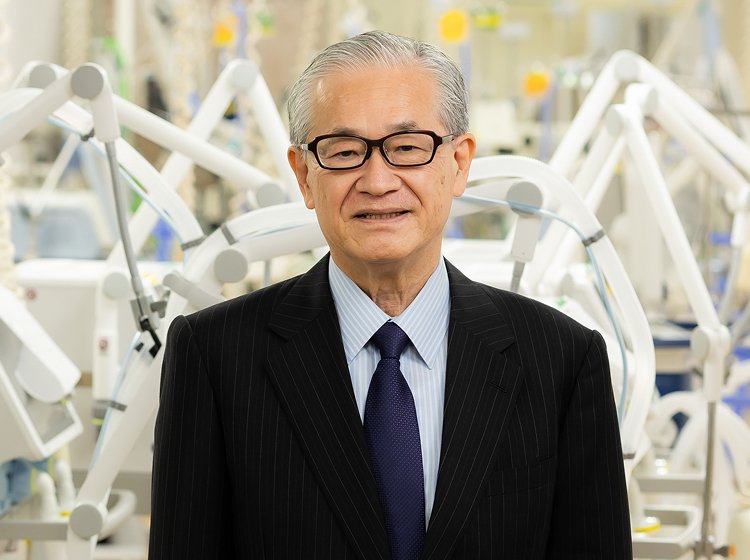
佐賀 俊彦
SAGA Toshihiko
名誉教授
Professor Emeritus
-
近畿大学医学部に初めて関わられたきっかけを教えてください。
1977年秋に城谷均教授が初代主任教授として着任し近畿大学に心臓外科を開設しましたが、まだ、近畿大学には自学から卒業生を輩出していませんでした。城谷先生から京都大学への要請で翌年1978年春に卒業した私が新卒研修医として派遣されたのが近畿大学との縁の始まりです -
心臓血管外科の主任教授として在職中、特に力を入れた診療・研究分野は何でしたか?
主任教授として着任した当時、臨床面で心臓外科全体が大きな転換期を迎えていました。新しい手術方法、より重症で複雑な手術への挑戦の一方で、手術の低侵襲化という二方向への発展が始まった頃でした。着任時、それらへの近畿大学の対応は後塵を拝していました。急速にあらゆる分野で先進へ押し上げてゆくことに全力で努力しました -
複雑心奇形や虚血性心疾患の外科治療において、近畿大学で実施した特徴的な手術や取り組みを教えてください。
バチスタ手術として知られる拡張型心筋症に対する左室縮小術の初めての成功例は近畿大学で得られました。ほぼ同年同月に行われた関東の他院で行われたバチスタ手術は、マスコミで大々的に取り上げられましたが、翌日に亡くなっています。その後も虚血性心筋症に対する新しい左室縮小術を開発し良い成績を上げることができましたが、この方法は非常に独創性の高い手術方法であったと思います。複雑心疾患に対しては初代城谷教授の時代に極めて複雑な複合心奇形に対する手術の挑戦が行われました。この時期に行った手術には、他院での実施の限界を超えるものが多くありました。 -
救急災害センター長、副院長として、病院運営や救急医療体制整備において印象に残っている出来事はありますか?
私が救急災害センター長になった当時は、それぞれ別々の経緯をたどっていたER部と救命救急センターの2次、3次救急の連携に難のある時代でした。組織改編を含めた取り組みで、機能の円滑運営に努めました。また、各診療科との連携の強化、運営マニュアルの作成にも努めました。南河内医療圏からの救急搬送件数を増やすために、私自身で何度も各地の救急隊へのあいさつ回りを行いました。 -
教授時代、若手医師や学生の教育で心がけていたことは何ですか?
まず、自分自身が心臓外科医として評価してもらえる、目標になれる技量、人格を維持できるように努力しました。陣頭指揮型であったと思います。学生には医師としての喜びやプライドを、また、心臓外科の面白さを伝えれるようにメッセージを発信し続けたつもりです。 -
海外勤務(オーストラリア)や国内他大学での経験が、近畿大学での活動にどのように活かされましたか?
オーストラリアでは実際に多くの手術を執刀する機会をえました。乳幼児の先天性心臓手術と成人に対する冠動脈バイパス手術の二つの領域を経験しました。特に近畿大学は冠動脈バイパス術の取り組み、実用化が遅れていましたが、私の帰国後、急速に近畿大学で冠動脈外科が発展する契機になりました。 -
心臓外科における低侵襲手術に関して、近畿大学での歩みや成果をお聞かせください。
心臓手術の低侵襲化にはいくつかの考え方があります。一つは心臓手術に人工心肺法を用いないこと。主任教授として着任して近畿大学で初めて人工心肺を用いない心拍動下の冠動脈手術(Off Pump CABG)を実用化させました。もう一つの低侵襲化は皮膚を小さく切開し、そこから心臓手術を行うという低侵襲手術。その先端がロボットによるよる心臓手術です。小切開手術の新しい技術開発に努め、発信しました。また、道のりは長かったですが、ロボット心臓手術の実施医の養成、実施施設の認定獲得などの高い壁を克服しました、もう一つの低侵襲法はカテーテルを用いた心臓大血管治療、カテーテルと従来の心臓大血管手術を組み合わせたハイブリッド治療の発展です。この領域も実施医の養成、実施施設の認定獲得、病院のハイブリット設備の新設などの大きな課題がありましたが、それら克服して実用化の軌道に乗せることができました。近畿大学はこれらのいろいろな低侵襲心臓大血管手術の先進施設となっています。私の主任教授時代はこれらの考え方が生まれ、急速に発展する時期と重なっていますが、新しい課題に絶えず先進的に取り組んでこれたと思っています。 -
新病院や医学部新キャンパスに対する期待や、今後の心臓血管外科の発展についての展望をお聞かせください。
新しいキャンパスの特性を生かしての発展を祈ります。心を込めて新病院を育ててください。教室の命は人材です。優れた指導者にバトンタッチすることができたのは私の誇りです。心臓外科、循環器内科の連携によるハートチームの考え方は、近畿大学の伝統ですが、近年、ますますチームワークが緊密となっていると聞いています。車の両輪となってますます発展するように祈っています。 -
近畿大学医学部でのご経歴を振り返って、最も誇りに思うことは何ですか?
スタッフ時代には城谷均教授という卓越した指導者にめぐり合うことができ、私の心臓外科人生が決定されたと思います。国際的にも通用する技量をみにつけていると海外勤務時代にも実感することができました。主任教授として赴任した時には臨床実績は低迷していました。在任19年で国内での基幹心臓外科施設に育て上げ、次代にバトンタッチすることができたことも誇りです。また、小さい教室ながら、伝統にある大学に伍して、心臓外科として要求されるあらゆる種類の実施専門医資格保持者の養成、実施施設の認定を獲得し、次世代にバトンタッチできました。