特色
経済学部ってどんなところ?
経済学と経営学の違いって?
経営学は、主に、「企業(組織)がいかに運営して成果を上げるか?」を探す学問です。これに対して経済学は「社会全体にとっての成果の向上」を探す学問と言えます。社会のさまざまなルールと、そこから生まれる結果に対し、「人々は大きな満足を得られるのか?」「より公平に富を分かち合えるのか?」といった観点から、よりよい社会に向けての評価を行います。
数学が苦手だから不安・・・
- 高校の先生による授業で、高校数学をもう一度復習できます!
(「特殊講義Ⅰ(数学入門)」) - 数学の基礎を使えば、経済学をより簡単に理解できます!
- 入試で数学を選択していない先輩たちも、しっかり講義を理解しています!
ITスキルの育成
資格取得を目標に、 体系的に学ぶことができる IT環境を構築
経済学部では、1人1台のコンピュータを利用した実習科目を開講しています。将来役立つOfficeApplicationの基本操作だけでなく、プログラミングなどの専門スキルやITに関する基礎知識も効率的に学ぶことができます。
- 格安で受験できるMOS※、VBA※試験を学内で実施
- KUDOS※や経済学部B館PC教室など、 最新のIT施設・環境を完備
- 少人数制を採用した情報処理関連の科目が充実
- ITパスポート試験や基本情報技術者試験に 向けたカリキュラムの導入
- MOS=Microsoft Office Specialist
- VBA=Visual Basic for Applications
- KUDOS=情報処理教育棟
少人数教育・実践的な教育
学生のニーズに応える充実のカリキュラムと少人数教育
一人ひとりの個性を伸ばす少人数教育
経済学部では、入学後すぐに少人数制の基礎ゼミがはじまります。めざす専門分野に必要な着眼点や考え方を学びながら、読む・書く・発表する・討議する力を養成します。

経済学をより深く学ぶために工夫された演習や講演会
演習I・II(ゼミ)
将来の進路に向けて専門的な学習を行うため、3年次から2年間、演習担当教員のもとで研究を深めていきます。
経済学部定例講演会
経済学部では年間約9回、学外から講師を招き、定例講演会を開催しています。東大阪税務署の協力による税に関する講演や、金融機関による日本経済や世界経済、業界、企業の戦略課題についての講演などを行っています。
在学生インタビュー
効率的な英語教育で語学力を育んでいます!
續池 永輝 さん
経済学科[3年]
大阪府・浪速高校出身
経済学部の英語教育は毎週ネイティブの英語に触れるので、英語に対するハードルが下がり、すぐに慣れることができます。少人数制の授業なので、わかないところがあれば気軽に聞ける雰囲気で、丁寧に教えてもらえることで理解力も深まります。また、他学科の学生と同じ授業では英語力の差に刺激を受けることもあり、モチベーションも高められます。今の目標は、英語スキルに必要な「読む・聞く・話す・書く」の4技能を極め、さらに語彙力を身につけ、英文で書かれた図書を詰まることなくスラスラと読めるようになることです!

卒業研究紹介
学科環境による成果の違いの分析
北原 英樹 さん
経済学科[4年]
三重県・三重高校出身
リモート授業など、学びの環境が多様化しています。学びの場所を自由に選べることは、学習効率にどのような影響を与えるのでしょうか。この疑問に答えるため、普段の教室と、洗練された雰囲気をもつアカデミックシアターでの学習達成度を比較する介入実験を行いました(N=54)。その結果、周囲の環境を良くすると暗記科目では約48%もの有意な成績向上が認められました。一方で、数学などの思考系科目ではそのような効果は認められず、学習内容に応じて環境を変えることが最善であるとの示唆を得ました。
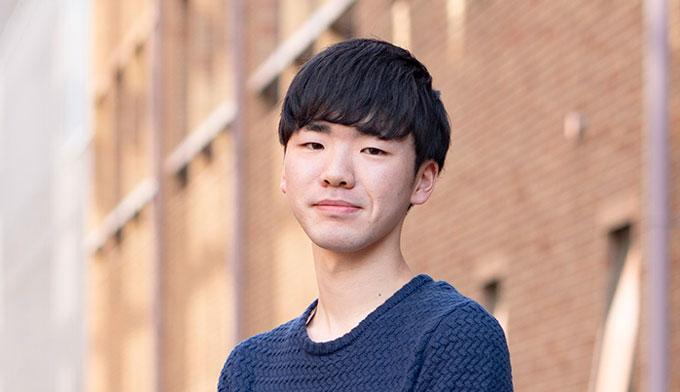
オリンピックは開催国にどのような経済効果をもたらすのか?
合木 大翔 さん
国際経済学科[4年]
香川県立高松桜井高校出身
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、異例の1年遅れかつ無観客での開催となった東京2020オリンピックの評価を含め、オリンピックが開催国にどのような影響をもたらすかを研究しました。過去のオリンピック開催から得られた直接的な経済効果や、新しい建築芸術・スポーツ文化の発展等の間接的効果を検証し、今後のオリンピック開催の是非を検討するための視点を提示しようと試みました。

読書の教育効果についての経済学的研究
新見 美幸 さん
総合経済政策学科[4年]
大阪府・大谷高校出身
近年、全世代において読書率が低下し社会問題になっています。読書と生涯賃金は密接に関係しており、読書習慣形成の有無が将来の生活にまで影響を及ぼしていることが調査により判明しました。特に、義務教育後の高校生段階において読書率低下が著しいため、対策を講じるべきだと考えました。そのため、教育の場である高等学校と本を提供する出版業界、読書週間形成を促す国の3方面に分け、各々の強みを生かした読書活動推進策を提案しました。
